|
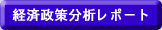
経済危機克服の戦略−ヒアリングメモ
(99.2.1)
ここでは政策シンクタンク「21世紀を考える会」における98年度フォーラムのパネルディスカッションの模様を収録する。多角的な視点での議論であり、参考になることが多い。筆者の都合で編集している部分もある。(文中敬省略)
| モデレーター: |
慶應大学総合政策学部 竹中平蔵教授 |
| パネリスト: |
京都大学 経済学部 吉田和男教授
東京大学 経済学部 伊藤元重教授
大阪大学 経済学部 跡田直澄教授
横浜市立大学商学部 藤野次雄教授
慶應大学 経済学部 塩沢修平教授 |
モデレーターの司会で、各パネリストが順々に話していくスタイルをとった。そこで、以下では、質問とその答えの要旨をまとめてみることにする。
【質問】現在の日本における「危機」とは一体なにか?
塩沢:
・危機と言い過ぎであり、それが逆に危機なのでは。
・その克服の為には、GDPの6割を占める個人消費の回復がポイントであり、それをこれからどう復活させるかが問題。
・買いたいものを買いたい価格で提供できれば、消費は伸びるのでは。
藤野:
・バブル後の調整と構造調整をどうやって同時に進めるかが問題。バブル後の調整とは、景気対策であり、構造調整とは、例えば社会保障の負担率の上昇と国債のための将来の増税予想などで財政の方針に対する不安が募り、不確実性で消費が落ち込む事態をどう改善するか、などである。その整合性をつける必要がある。それが今はついてないのが危機の1つ。
・メインバンク・終身雇用などの制度・規制・慣行を、この10年間のグローバル化で変化して大きくなったフレームワークの中で合理化するかがポイント。このフレームワークの中では、慣行などは説得的ではない。これをどう調整するか、という試行錯誤の危機である。
跡田:
・何をしたらよいかが分からない不安感が危機である。
・今はバブルの失敗など何かにつけ悲観論が支配している。
・何が間違っていたのかの整理が必要。
・政策決定のバワーバランスが変化している中で、指導層の自信回復が必要。
元重:
・アン・クルーガー(有名な経済学者で元世銀副総裁)は講演の中で「21世紀中頃の歴史家が20世紀後半を記述する時は、『世界の多くの国がこれだけの高い経済成長を維持した時期は他にない』というのを抜かさないであろう。」と言ったが、確かに20世紀後半は高度成長の時代であり、例えば日本のGDPは
1950 世界GDPの2%未満バブル期 20%近くまでとなり、日本は「奇跡の国」といわれた。その際に出来た仕組みがメインバンク制であり、奇跡と共にしか維持できない仕組みなのである。今は少なくとも奇跡の成長期ではないという事を認識してシステムを変換しないといけない、という意味での危機である。
・大きな転換は難しい。タイタニック号も転換は簡単ではなかった。
・東南アジア・中国・ロシア・ラテンアメリカという80年代にエマージングマーケットといわれた地域は、当時急激に成長し、今は危機に陥っている。成長を支えたのは、先進国の投資と国際貿易の拡大であった。急に走り出した経済は市場主義に対応できないのである。企業会計や税制のあいまいさなど制度面の整備が出来ていない、という矛盾があり、それが露呈した形である。
・21世紀に市場の力を抑えてもとに戻るのは無理ではないだろうか。よく資金の流れは自動車や航空機みたいだと言われる。徒歩と自転車だけだと事故はない。しかし自動車や飛行機が開発されると、みんな乗るようになる。便利だが、当然これまでにない危険も増し、事故も増える。それでもみんな乗るのである。ではどうするか。
それを安全に使いこなす為の努力、資金で言えば、どう取り込んでいくか、がポイントになってくる。
吉田:
・現在は複雑な仕組みが相互に影響を与えている時代である。複雑系の考え方が重要であるが、ただし複雑系では原因と結果は分からない。また仕組みが
うまくいってる時は安定していてうまくいってない時は不安定になる。
・アジアの奇跡においても、リスク評価の数値化などの技術が、システムを安定させると予想されていた。タイでは、経常収支の赤字が続いていたが、それを短期資本でカバーしていた。結果として貯蓄と、流出の額が同じでバランスが取れていなかった。デリバティブなどの金融技術でそれが安定的になると予想していたのである。結果として崩壊してしまった。もちろん資本流入がなければ成長もなかったのだが。
・現在の貸し渋りは、早期是正措置に対応したものとなっている。結果として「リスクアセットを減らす」となっている。だがそれだけが原因ではない。今は担保主義であるが、1昔前は違った。「担保の回収率は低いので、それで回収できるとは考えていない。せいぜい掛け目率は6割くらい」として昭和50年代は担保など信じていなかった。ところが現代は担保に頼っているので、それがなくなるとどうしていいか分からない。すなわち「あほ」になっているのである。それが今の危機である。
【質問】 ポリシー・クライシスと言われている現在において、緊急避難的な政策が続いているが、その評価は?
跡田:
・バブル後の極端なケインズ・ポリシーは一応景気を下支えしているのではないだろうか。
・本来的な効果はまた別の問題で、それは疑問が残る。もちろんある程度の経済効果はあるはず。最低でも下支えに使ったコストが回収できているかどうかがポイント。少なくとも5年で回収できないと効果があったとは言えない。
・税や利払いを含めて、ほぼ3倍の効果があって初めて意味があるといえるがそれは今や現実的に無理なのでは。
塩沢:
・金融機関の破綻ルールが出来つつある。これまで金融機関は、量が多く、借り手を探す能力などにかけていた。これからはルールの設定によって、金融機関を減らす事が可能になるのでその点は評価したい。
・景気対策の財政支出については、これからは中身を変えないと駄目なのでは。
元重:
・財政政策についてはコメント程度にさせていただきたい。実は正月風邪を引いて寝込んでいたのだが、夢の中にマルクスとケインズが出てきて世の中を悪くしていた。やはりこの2人が出てくると景気が悪くなるのだろうか。
・金融については、経済戦略会議でその担当だったこともあり、そのメンバーの共通認識を交えてまとめてみる。
日本の金融には大きな矛盾があると考えられる。現在の国民の資金の多くは、元本保証のウェイトが大きい。しかしながらその資金はリスクのある先に投資されているのである。設備投資でさえもリスクはある。例えば郵便貯金は、当然元本保証で、その総額は東証の株価総額を超えていると言われるが、その運用先にはリスクがあるわけである。
この矛盾の解決の為にはリスクの取れるように資金を流す必要がある。アロー・リーンの定理によれば「リスクは1人で抱えるよりも10人で抱えるとリスクは100分の1になる」のである。
方法論としては、個人レベルでは、マーケットとの関連においてデリバティブを使用した投資信託などが成長する必要がある。また企業レベルでは、ノンバンクが発行するCPなどの発達が必要で、そのためには、CP発行の為のいわゆるファイナンスカンパニーなども必要である。例えば不動産に関しては、ビルの証券化による分散投資など、ノンバンクの役割が大きくなる。
これらは制度的な矛盾であり、法制度の整備も必要であるが、中長期の課題でもあるので、早急に行う必要がある。
藤野:
・メインバンク制などは、日本経済の成長によって発達したといわれるが、そうした外的環境がなくても発達したのではないだろうか。
・これからの金融は、いわゆる仲介業と、流通だけでなく製造業的な役割に2極化するのではないか。
・日本人のリスクプリファレンス(リスク選好)が不変かどうか、というのも問題のはず。情報弱者の存在もあり、これが制度によって変化するのかは疑問。果たして投資信託は増えるのだろうか。教えて頂きたい。
・財政政策については、逆説的だが、学者がケインズポリシーをきちんと教え過ぎたから、効かなくなったのではないだろうか。
元重(藤野先生の質問を受けて):
・日本人のリスク選好については、郵便貯金もあればJRAもあるので、やはり制度・仕組みの問題と考える。
例えば、10年前にある都銀の幹部と話していて「日本人はつつましやかだから、支店の窓口でボードで金利を比べる事などない」と言っていたが、制度が変わった5年後には窓口には金利ボードが並んでいた。
・情報については、よくニワトリと卵の関係のようだといわれる。誰かにまかせておいたら安心しているが、その実体を知らされたら身構える。その意味では、実体を知らせればあるレベルでは情報を取れるのかな、と思う。
企業戦略としてもそれは重要で、その例として、メリルリンチでは、経営を立て直す為の支店長会議の議事録の中で、「これまでの墓石広告を素人にも分かるものに変えないといけない」を柱として打ち出している。
・どの人も、命に関しては、医者や薬など、非常に注意を払う。命の次に金が大切とすると、せめて「命」の10分の1くらいの注意を向けるべきではないだろうか。すなわち資金運用についても情報を積極的に活用すべき。
吉田:
・今の企業は含み計をしているから償却できない。これがなければバブルは防げた。
・システムを変える為の議論の場を作らないといけない。システムを変える時にはいくら金を使っても無駄である。
【質問】いわゆる「小さな政府」論が主流になっているが、それを推進する事で本当に経済は成長軌道に乗るのか、不安が出ると逆に消費は減るのでは?
元重:
・「小さな政府へ移行だと将来の不安を引き起こして、消費を減らして国民の貯蓄率が上がる」というロジックは認識がちがう。
今の「大きな政府」が国民に信任を得ているかどうかがポイント。あまり国民から信任を得てないのではないだろうか。サイズの問題ではなくて「やることはやる」「やらなくていいことはやらない」ようにすることがポイント。
・政策が信じられていないのではないか。「民間主体」にしても国民がどう受け取るかは不確定。消費の問題にしても、消費税を下げた後どうなるのかは分からない。将来の増税を予測して、消費は増えないかもしれない。長期的な視点を出す事が必要なのである。
・学者は、色々な人を説得しないといけない。特に新聞などの中でも頭のかたい人をどう説得するかが問題。
竹中:
・小さな政府論を考える時に、セーフティーネットをどこに求めるか、も問題。これまでは「企業」が企業年金や終身雇用でその役割を果たしていた。
それに代わるものは政府だろうか?それはおそらくない。「教育」ではないだろうか。教育で人的資源の価値を高める必要がある。これがセーフティーネットになるのでは。
・また説得は、政治家とメディアの責任が大きい。(小渕首相の戦略会議の中間報告を見ての発言に対して)「これ全部やったら日本はよくなるね」>他人事みたいに言わないで下さい。「僕ももっと長く首相やりたくなってきたよ」>それがいい事かどうかは分かりませんが。
【質問】どんな議論システムを作ればよいか
吉田:
・システムの議論の場・仕組みを作る必要がある。しかし、システムの議論は利害があるのですぐやめてしまう。政策を多元的に議論しないとだめ。
・アメリカのシースパン(テレビ局)は国会中継を絶え間なく放送。日本にはこうした対案を出して議論するというディベートの仕組みがない。これを生活習慣に入れてもよいのでは。もちろんそれだけになっても疲れますが。
【質問】効果ある公共投資・社会資本整備とは?
跡田:
・短期的にも長期的にも否定的。生産力に寄与する社会資本設備が必要だが、それは情報関係のみであろう。
・社会資本整備は生産性を考慮したものと、生活を考慮したものに分かれるが、前者は借金しても返済されればやってもいいが、後者は借金してまでやるものではない。
なぜなら後者は生産性に寄与しないからである。
・政策のプロセスを全部公開する必要。学者などの作った理想論を、政治のプロセスなどで、誰がどのようにゆがめているかを公開すればよい。
吉田:
・ミュンヘンは公共投資はGDPの1%にすぎないが効果的である。それでハブ空港、見本市改革、大学の3つに投資して成果を得た。大学は非常に重要。「ソフトを作るためのソフト」というインフラである。
【質問】今、誰がどういうトリガーをひかなければいけないか?
吉田:
トリガーをひくのはあなたです。全ての人が自分でやらないと駄目。先生自身も
教育がおかしい→月1回の私塾を開いている
金融がおかしい→ベンチャーキャピタルをつくる努力している
と実行しているように、結局自分でやらないと駄目。
元重:
政治と経済の改革は違う。政治改革は派手ではあるが、何も残らない。経済改革は、目にみえない胎動が重要である。マイクロソフトも、何人かの若者があるガレージから生まれ、いいにつけ悪いにつけ話題にのぼるヘッジファンドもイトウ方程式をシカゴ大学などの学生が紙の上で議論したものがスタート。(イトウ方程式は元重先生とは関係ないそうですが)
すなわち、1人1人がそれぞれの引き金を引く責任を持っている。柳沢金融担当大臣は日債銀問題などの金融再生のトリガーを、銀行首脳はリストラのトリガーを、小渕首相は様々な決断のトリガーを引かなければいけない。個人個人みんなそれぞれ役割がある。
跡田:
日本を開国することが課題。自国だけでマーケット化はまだ無理。外国資本を大量に導入したり、人の流入も促進する。明治初期のように閉鎖的システムを開放すること。特に金融セクターはこれが活性化の鍵になる。
藤野:
新しいシステムを提供していく側の信認を得るための努力と、受け入れていく側の情報の解釈と信認、という信認の需要と供給のバランスがくずれているのではないだろうか。そのためには競争して、信認を取る為に両方とも努力する必要がある。コストを考えて自分の生活をファイナンスするようになればいい。
塩沢:
この時代に必要なのは、まさに福沢諭吉の「独立自尊」ではないでしょうか。(この日は福沢諭吉の命日ということで、慶應の先生らしいコメント)政府に対応を求めるのではなく、我々の手でやるという発想が必要。
竹中:
気力の心理学によると「やってもやっても無駄で達成感がない」「何もしなくても与えられる」の場合無気力になる。日本の経済システムもまさにこの2つがあてはまる。
規制・慣行だらけで、ようやくそれをくぐっても税金で沢山とられる。一部の地域・産業・企業は何もやらなくても与えられる。解決の為には独立自尊の精神で、みなさんが自身でトリガーをひくことが必要。また政策を多元的に議論する場を社会に作る必要。
|
