|
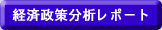
構造改革について(200110.21)
先週金曜日(10月19日)に、与党の政策懇談会、経済財政諮問会議で、財務省が 提出した補正予算が了承されました。国債発行30兆円の枠を守るかどうか、が大き
な焦点になっていましたが、30兆円の枠を守った予算案になりました。
これは小泉さんの提唱する構造改革の中の、財政構造改革の一環ですが、そもそも
構造改革とは一体何なのでしょうか。
■構造改革とは何か
小泉さんの提唱する構造改革は3つに分かれます。「骨太の方針」や所信表明演説 にもありますが、1つは不良債権処理、2つめは規制緩和などによる新規産業の創
出、3つめは財政構造改革です。これらにより、経済・財政の構造を変革し、中長期 的な成長力を身につけて、日本経済の再生を図る、というのが目的です。
■プラスの面とマイナスの面
ここで不安になるのは「中長期的にはいいかもしれないけど、この不況の中でやって いいの?」という点です。中長期ではプラスの一方、短期的にはマイナスの面も出て
くるからです。それぞれまとめると、
【マイナスの面】
・不良債権処理によって、倒産するところが増え、失業も増える。
・このデフレ下だと、不良債権処理により、一層デフレになる。
・財政構造改革で財政支出が減り、財政による景気の下支えが弱まる。
もう少し財政で下支えをして、景気がよくなってから構造改革してもいい。
【プラスの面】
・社会全体が変化し、競争的で活発な経済社会になる。
・規制緩和で、新しい産業が創出され、雇用も増える。
・不良債権処理で、企業のバランスシートがよくなり、投資が増える。
・財政構造改革で、財政が健全化し、金利も安定する。
・中長期的な潜在成長力が高まり、日本経済が持続的成長パスにのる。
などです。筆者は構造改革推進派ですが、マイナスの面に対してコメントすると
・不良債権処理による失業増
→小泉内閣は、短期的な失業をカバーするため、雇用のセーフティーネットを同時に
政策に盛り込んでおり、さらに中長期の方にある雇用創出で対応
・デフレの深刻化
→柔軟な金融政策で対応する一方、デフレは将来の期待にも左右されるので、中長
期の経済成長の期待を形成することが解決策になるのでは
・財政の下支えが必要
→これ以上の財政支出は、需要創出効果はあるものの乗数効果は落ちており、長
期金利上昇のリスクを考えると、相対的に経済にとって望ましくない
■今後の政策的課題
現在のところ、小泉さんのリーダーシップで推進されていますが、今後、実際に自分
の周りで、失業など構造改革の痛みが出てきた場合、「将来よくなると言うけど、今
は痛いし、本当に将来よくなるのか」と不安になります。一般に人間は近視眼的なの
で、「今の痛み」の方が大きく感じ、結果構造改革に反対することもあります。そこが
辛抱のしどころなのです。
最大のボトルネックになっているのは、構造改革が終わった後の日本が見えにくいこ
とだと思います。単に「もう少し待ってて」では、期待が持てません。きちんとしたシナ
リオでもって、今後の日本の姿を描くべきです。
一般的なマクロモデルによる試算では、構造改革は、供給面の生産性上昇に取り入
れられるだけです。ただ小泉さんの目的と手法を実践した場合、規制緩和により労
働力が増加したり(一時的には失業率が上がるかもしれないので、相殺?)、新規
産業創出によって民間投資が増加するなどの効果もあります。それらを考慮した試
算も必要でしょう。
また上述のように、構造改革には短期的にはマイナスの面もありますが、長期的に
はプラスの面もあります。留意しないといけないのは、長期的なプラスの面は、スタ
ートが遅くなればなるほど、効果が小さくなることです(例えば、財政構造改革は、ス
タートが2年遅れると、同じ水準を達成するのが5年遅れるといいます。その分利払
い費も増加します)。これも示すべきです。
そこは政府の責任もあり、構造改革が終わったら日本がどうなる、ということを抽象
的に表現するのではなく、それぞれの改革がどのような効果を持つか、明示すること
も重要です。いまだ小泉さんの支持率は高く、それは構造改革に対する国民の期待
もあるでしょう。改革成功のためにも、政策の中身だけではなく、実施プロセスも戦略
的に構築するべきでしょう。
|
