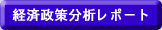
持株会社と独占禁止政策の整合性(00.9.21)
戦後、健全な競争を阻害する「独占」を防ぐために独占禁止法が制定され、公安委員会によってカルテルが摘発されるなど、公正な競争が行われるようにそれなりに機能してきました。
独占がなぜよくないかは、ミクロ経済学では初歩的ですが、軽く復習してみましょう。
完全競争の世界では、逆需要関数と限界費用線の交点まで生産して、そこで価格が決まります。ところが独占の場合は、限界費用線が限界収入線と交わるような点が実現するように数量を調整できるので、その数量調整によって、価格が上昇し、いわゆるDead
Weight Lossが発生して、社会厚生が減少してしまうわけです。
(経済学部出身の方には、なつかしい言葉達なのではないでしょうか?)
# 完全競争:P(価格)=MC(限界費用)/独占:MC(限界費用)=MR(限界収入)
さて、金融持株会社を含めた持株会社を解禁する政策は、確かにグループ化をすすめ、独占か寡占の状況を生み出しますが(現に金融グループはすでに3つ程度)、上記の独占の弊害はどのように考えたらよいのでしょうか。
それはコンテスタブル・マーケット(Contestable Market)の考え方です。簡単にいうと、実際マーケットが独占の状況であっても独占価格にはならない、というものです。(銀行だと操作変数は金利でしょうか)
ロジックは以下のとおりです。参入・退出にコストがかからないマーケットを考えます。その時に独占企業が価格を限界費用よりも高くしたら、新規企業が参入して、少し安く価格を設定すれば、みんなそっちを買うので利潤を上げることが可能になります。すると独占企業の価格が限界費用よりも少しでも高い限りは、新規企業にとっては参入のインセンティブがあるので、独占企業にとってこのヒットアンドラン戦略の脅威は続き、結局独占企業も価格を限界費用と同じに設定するということです。
つまり、この理論によれば独占市場でも、実質的には完全競争と同じ状態になるわけです。(厳密には他にも仮定が必要ですが)
さて、これを日本の金融業界に応用するとどうなるでしょうか。
現在のように、日本で3つの金融グループに収斂して市場が寡占状態になっても、そこで独占利潤を獲得するための行動(高い値段をつける)をとったら、異業種参入や外資系金融機関など外部者が市場へ参入して、利益を失うことになります。現在は異業種参入や外資系への許認可も緩くなったので、ますますこの状況になりつつあるといえます。そこで、日本の金融グループは独占企業的な行動には移らないと考えられるのです。
というわけで、独占禁止法と今回の持株解禁は、経済学的には矛盾しない政策とも考えられるのです。
また今回は理論と結びつけて解説しましたが、
| ・ |
むしろグローバルな金融マーケットで生き残るために、やむをえず手を結んだ |
| ・ |
すでに外資系が入ってきていて、寡占状態ではない |
| ・ |
参入や退出はいまだ自由ではない(許認可もコストとみることは可能) |
| ・ |
現在は政策的な低金利なので、競争はもともと出来ない |
など実体面の現実もあります。
|
